私が,ビジネスパートナーを選ぶときは以下のような方がいいです(順不同)。
・仕事ができる(当然ですが)。
・何事も早い。話しも早い。
・明るい。
・根性がある。簡単にあきらめない。
・上昇志向が強い。
・遊び好き。
かくいう私自身も,かくありたく努力しています。ビジネスパートナーたるもの,お互いが昇り龍のように天まで昇れればいいですね。
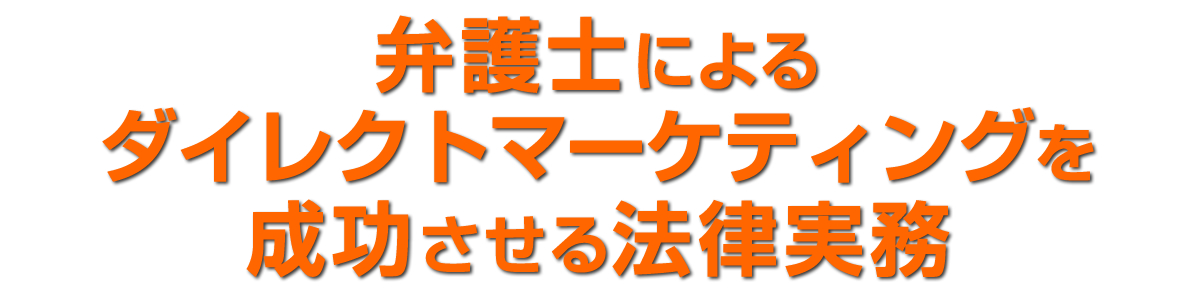
私が,ビジネスパートナーを選ぶときは以下のような方がいいです(順不同)。
・仕事ができる(当然ですが)。
・何事も早い。話しも早い。
・明るい。
・根性がある。簡単にあきらめない。
・上昇志向が強い。
・遊び好き。
かくいう私自身も,かくありたく努力しています。ビジネスパートナーたるもの,お互いが昇り龍のように天まで昇れればいいですね。
プロとアマの実力差は圧倒的です。私も弁護士業以外ではプロの方の力に大いに頼っています。実力差をよくわかっていますから。
プロとアマが対決すると何が起こるのか。最大の違いは以下のとおりです。
プロの側は,相手方が何を考えているか,何を考えてそのような行動をとったのか,次にどのようなことをしてくるのかがクリアに見えています。それに対し,アマの側はプロの行動が読めていません。要するに,アマの側は,プロの掌の上で転がされているのです。これでは勝ちようがありません。
経営者たるもの自分のフィールドでプロでなければならないと思います。そして,ビジネスで組むのもプロと組まなければいけません。
もっとも最近は「プロ」と称するアマが世の中には多いので要注意です。
天地雷動(伊東潤)。もう半分くらい読み終わりました。ネタ的には作者の得意分野で過去の小説ともかぶりますが,そのようなことは全く関係なく読ませます。
「タックス・ヘイブン」(橘 玲)。出たら読みます。橘玲の本は,細部がいつも興味深いです。
「オーパ」シリーズ(開高健)(再読)。もう何度も読んでいます。今年のGWはどこにも行かないので。
「現実を視よ」(柳井正)(再読)。GW明けのビジネスに備え,自分に活を入れ,戦略を考えます。
「剣客商売」(池波正太郎)(再読)。何度も読んでいますが飽きません。池波正太郎の小説では一番好きです。Kindleで全巻そろえたのでだらっと読みます。
「ボックス!」(百田尚樹)(再読),「七帝柔道記」(増田俊也)(再読)。最初は弱かった主人公がハードトレーニングで力をつけていく。鉄板の王道小説ですが,それでもはまります。やる気を増幅させるために。
皆様も興味があれば読んでみてください。
私は,顧問弁護士として,また委任を受けて,様々な交渉を多く行っています。今回は,交渉の中で経験してきた,特に日本人にありがちなよろしくない交渉姿勢について書きたいと思います。
最大の問題点は,交渉決裂を必要以上に怖れる,主張すべき事を主張しないということです。その際の心理状態は,「事を荒立てたくない。」「相手方を怒らせたくない。」というものです。そして,「まあ,良い交渉ができた。」「相手方もこちらが譲ったことを分かってくれている」「ここで譲っておけば,次のときに譲ってもらえる。」などと合理化します。
たしかに,そのような場合もないとはいいません。しかし,たいていの場合,「恩返し」されることはないです。むしろ,次から次へと要求を繰り出されてしまいます。必要な主張をしたことにより壊れてしまうような関係なら早く壊す方がいいですし,企業としてはその時点その時点での利益を徹底的に追求するのが大事です。
交渉における負け癖は尾を引きます。
交渉は徹底的にやり,まとまったら交渉経緯はお互い忘れて仲良くというのが大事です。頑張って交渉していきましょう。
弁護士と裁判官は法律家というくくりでは同じような職業ですが,実際の業務は大きく違います。
弁護士は,「代理人」ですので,依頼人の立場に立ち,依頼人にとってベストな解決をするために知恵を絞ります。裁判官は,中立の立場で判断をします。
ところが,弁護士の中には裁判官的に中立の立場で結論をだして,それを依頼人に伝えるだけという人もいます。依頼人は,「自分はこうしたい。こうあってほしい。しかし,自分は法律はわからないから専門家に自分の考えを実現して欲しい。」と考えています。それなのに,「それは法律的に無理です。」では専門家に頼んだ意味がありませんし,がっかりです。悪条件でも,「何とか結果を出す。」のがプロの仕事だと思って私は業務を行っています。良い代理人たらんとすれば,「評論家」ではなく「実行者」でなければいけません。
依頼人は,事実関係等については一番詳しいですし,強い思いもあります。じっくり話を聞いてみると,別の角度から解決への糸口が見つかることも多くあります。
どんな業種でも,「素人は何も分かっていない。」などと見下さず,よく話を聞いてみれば,そこには思いがけない宝が埋もれているのではないでしょうか。
出張や私的な旅行で平均して年4,5回は海外に行きます。今では,海外にいても国内と同じように仕事ができますので問題ありません。例えば,顧問弁護士をつとめている顧問先様などとはお互いよく分かっているので,電話やメールで事足ります。ちなみに,私自身は日常の延長で海外に行っている感覚ですので出張中に普通に国内のお客様と仕事をしていても全然違和感がありません。
私自身は,海外に行くことは,必ず,かけた時間とお金以上の価値があると考えています。具体的には,(1)現地でがんばっている人を見ると,自分もがんばらなければと思う。(2)日本と異なる状況を見ることにより,健全な危機感を抱くことができる,(3)環境の異なるところで思考することにより,日頃思いつかないビジネス上のヒントが多数得られる,(4)実際に海外での事業展開への意欲・ヒントが得られる,などでしょうか。その他にもいろいろあると思います。
まずは,どんな形でもいいから,とにかく海外にたくさん行くことが大事だと考えています。
リスク管理というと,すぐに難しい話しが始まるのが通例です。費用もそれなりにかかります。しかし,その前に,以下の3点がしっかり実現できているかを確認されるだけで大きな効果がありますし,逆に,これらの基本ができていなければ,いくら高度なことをしても無意味です。
1 最大リスクを認識する。性悪説で考える。
2 目に見えるかたち・証拠を残す。
3 その行動をきちんと「説明」できるか。
1については言うまでも無いことです。費用もさほどかからないはずですが,人は自分が見たくないものは見ないという強い習性がありますので気を付ける必要があります。2については,いくら適切なリスク管理をしていても,「かたち」として残っていなければ「何もしていない」ということと同じに評価されてしまうと考える必要があります。日々,何事も記録化することが非常に重要です。
最後に3についてです。リスク管理は,将来のことを想定した動きなので,問題の発生を完全に防ぐことは困難です。また,コストの問題もありますし,利益を得るための企業活動をしないといけないのですからリスクを全くとならないこともできません。そこで,重要になってくるのが,「何故そのような行動をとったのか」と合理的にきちんと説明できるようなシナリオを作っておくことです。きちんと説明さえできれば,結果として問題が発生しても,さほど大きな問題にならずに切り抜けられます。そこには,「見解の相違」はあるかもしれませんが,見解の相違にすぎない場合には,相手方やマスコミ等の第三者は当方を強く攻撃することはできません。しかし,当方がきちんと説明できず,不合理な弁解を繰り返すばかりでは,相手方の攻撃は徹底的なものになるばかりでしょう。現代は,自己責任の時代です。このような適切なシナリオづくりがいつもできているか否かが企業の死命を制するといっても過言ではないでしょう。
STAP細胞の問題について当てはめて考えてみましょう(STAP細胞の存否ではなく,論文の写真等の問題です)。先ず,写真の不適切な使用がここまでの問題となると認識していたでしょうか。次に,きちんとかたちが残っていたでしょうか。実験ノートは2冊だけなどと報道されています。最後に,写真の差し替え等をきちんと説明できるでしょうか。科学の世界であのような説明ではとおらないでしょう。そういう説明をできない行動をしてしまった時点でリスク管理としてはアウトということになります。
英語での法律相談を受けたり,英語で相手方と交渉をしたりすることがときどきあります。
最近気づいたのですが,特に英語を勉強しているわけでもなく,むしろ英語からは遠ざかっている環境なのですが,弁護士になりたてのころより,明らかに法律相談や交渉の際の英語力がアップしてスムースになっていることに気付きました。
理由は,弁護士としての力がアップし自信もついているので,その状況で使うべき単語・表現も迷わずにすぱっと浮かんでくるからだと得心しました。語学は,ツールですので,中身がなければ,その言葉は武器にはなりません。
英語は,発音等がいまいちでも十分に使えますし(流麗である必要は全くありません),グローバル化の中での世界共通言語であることは間違いないので,経営に携わる方は臆せず仕事で使って行かれたらいかがでしょうか。
ビジネス上では経営者自らが必要な場面で使うことは必ずプラスになります。最近,野球・サッカーで海外でプレーする選手も多いですが,日本語しか話さずいつも通訳をつけている人と,下手でも現地語もしくは英語で話す人ではどちらが成功するか(単にプレーだけではなく,もっと大きな意味での成功という観点からも)は明らかです。
マイケル・ジャクソンが1988年にリリースした曲です。曲も歌詞もマイケルのパフォーマンスもすばらしく,今聞いても全く古くなく,私の中ではマイケルのベスト3に入ります。
Man in The Mirror はいうまでもなく,自分のことです。世の中を良い方向に変えるためには自分が変わらなければいけないというメッセージが繰り返されます。といっても,まったく押しつけがましくなく,自然とそのような気にさせる曲になっています。
経営も,経営者自身が変わらなければ,会社は変わりません。私は,この曲を聴くと,いつもそのようなモチベーションが上がります。
皆様にもお勧めします。
仕事柄,さまざまな紛争や交渉に関わり,その顛末をみとどけます。また,事業の展開等についてもいろいろなケースを見てきています。
そのような中で,よく経験するのは以下のようなことです。
「大欲」,(大きな目標といっても良いです)を掲げてそれを目指すことは非常に良い結果をもたらす場合が多いです。それに対し,「小欲」,せこい利益取りを目指したり,小さな点にこだわる場合は,まずい結果になる場合が多いです。
例えば,難しい和解交渉でお金も全然取れなそうな状況だったとします。そこで,知恵を絞って,2億円を勝ち取れる状況になったとしましょう。これは,「大欲」を持ち張った結果が産んだものです。あるいは,自分が1億円払わざるを得ない状況で,1000万円まで減らしたというのも同じです。
ところが前者の場合でいえば,あと100万円などと欲張って,話しを壊す場合があります。後者の場合も,1億円払うところが9000万円減ったのですから万々歳なはずですが,あと50万円減らそうととか細かい条件をつけて,話しを壊しもとの木阿弥で1億円払わざるを得なくなることもあります。
人はえてして,大欲はもたないのに,小欲をもちがちです。人間心理からするとありがちなことではありますが,注意したいものです。